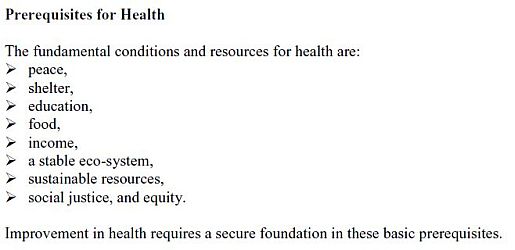
- 平和
- 住まい
- 教育
- 食糧
- 所得
- 安定した生態系
- 持続可能な資源
- 社会正義と公正(公平)
テキスト「シンプル衛生公衆衛生学2008」では,4-3「健康増進」pp.57-67,6「環境保健」pp.113-186に該当する。
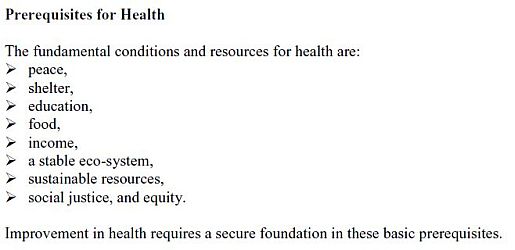
「健康増進(health promotion)は,よい行動を勧めて,人々をより健康の方にもっていく」とテキストにあるが,オタワ憲章で提唱されたのはもっと広い概念。健康な生活習慣としてだけでも,衣食住を含む下記があるし,先に挙げた「前提条件」が満たされた上で,健康に係るさまざまなセクターが協力し合わなくては達成できないということが強調されている。
数値目標を出した具体性はいいのだが,食生活という視点が薄いかもしれない。
「人間の健康はその人間が生きていくための生態学的条件が保全されることによって初めて成立する」という考え方
ヒトが自然生態系の一部として暮らしているような社会では,人々は,自己の健康が生態系の健全な回転によって支えられていることを知っている(たとえ健康とか生態系という概念について自覚的でなくても)
(例)長期間にわたる参与観察を行い現地の呪医にまでなった掛谷誠は,西部タンザニアの焼畑農耕民トングウェの生活を詳述している。それは,トングウェにおける生態学的健康観の実在と,それに立脚した広義の保健医療活動が呪医によってなされていることを示している。作物や獲物が豊かに手に入ること,配偶者や子宝に恵まれること,疾病にならないこと,などがすべて一貫したものとしてここでは考えられていて,これらすべてをまとめたものは生活の場で捉えた健康ということができる。生態学的といえる。
健康が生態学的に捉えられていない=生活圏と生活の場の乖離が起こっている先進国社会でも,生態学的健康観は残っている
生物(organism)にとっての環境(environment)とは,それ自身を取り巻くすべてのもの
環境には生物的環境(他の生物)と非生物的環境(温度,降水量,土壌中化学成分など物理化学的条件)がある
生物は環境から資源を取り出し利用することで生命活動を行う。逆に見れば生物が生命活動を行うことで環境を改変する。中でも人間は,その環境改変能力が大きいことが特異的
環境から生物への働きかけを環境作用,生物から環境への働きかけを環境形成作用と呼ぶ。これらを1つのシステムとしてみるとき,host-environmental systemと呼ぶ。
鈴木庄亮:人間の環境を生活の場(habitat),生活の資源(resource),環境要因(environmental factor)の3つに分けてそれぞれを捉える
鈴木継美「人類生態学の方法」(東京大学出版会):人間=生態系を言語,技術,社会組織を通じての人間と環境の相互作用と捉える
この把握では,テキストに生活の場の例として挙げられている家庭,学校,職場,公共諸施設,輸送機関,といったものは,環境そのものではなく,環境と人間をつなぐ技術や社会組織という捉え方をすることも可能
人間が環境を変化させるのに伴って,当然,環境から人間への働きかけも変わってくるので,病気や健康の質も変化する。また,個体群レベルでみれば,人口規模の影響も大きい。
| 1985年以前の年数 | 何世代前か | 文化状態 | ヒトのコミュニティ規模 |
|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 50,000 | 狩猟採集 | 100人未満の遊動的なバンドが散在 |
| 10,000 | 500 | 農耕の発達 | 300人未満だが比較的定住化した村 |
| 5,500 | 220 | 灌漑農耕の発達 | 多くの村は300人未満,いくつかの10万都市 |
| 250 | 10 | 蒸気機関の導入 | いくつかの50万都市,多くの10万都市,1,000人規模の多くの村 |
| 130 | 6 | 衛生状態の改善 | - |
| 0 | - | - | いくつかの500万都市,多くの50万都市,1,000人規模の村は減少 |
出典:Mascie-Tailor CGN (1993) The Anthropology of Disease, Oxford Univ. Press.より私訳
生物圏(biosphere)は,地圏(geosphere),水圏(hydrosphere),気圏(atmosphere)の接点に存在。ほとんどの生物は,土壌,大気,水のすべてを必要とするから。
地圏:地球は半径約6400kmの球体(やや歪んでいる)。中心部の半径約1000kmの部分は固体。その外側の約2000 kmはニッケルや鉄が溶けた高比重の液体。その外側約3000kmはマントル(マグネシウムや鉄に富む岩石)で,ゆっくり対流。その上に厚さ5 km〜60 kmの(海洋底で薄い)地殻。地殻の成分はアルミニウムや二酸化珪素などが主。地殻は海洋底でマントルが上昇してきたところで形成され東西にゆっくり(毎年数センチメートル)移動。逆にマントルが沈み込むところは火山帯になり,ミネラルに富んだ溶岩を地上に吐き出すので土壌が肥沃になる(日本列島など)
気圏:海抜13 kmまでを対流圏,その上の17〜30 kmの層を成層圏という。現在の窒素4:酸素1という大気の組成は,植物を中心とした生物の環境形成作用の産物。
水圏:地球上の水のある部分。97.5%は海洋にある。真水は2.5%のみ。真水の70.2%は極地の永久氷,29.3%は地下水(湖沼,土壌水,水蒸気,河川,動植物水として存在するのは,真水の0.5%のみ)。
生態学(ecology)は「生物の分布と豊富さを決める相互作用の研究」(Krebs,1972)であるが,個体,個体群(同種の生物の集まり),群集(複数の個体群からなる)という3つの水準で扱うのが普通(Begon/Harper/Townsend,1990)。
個体(organism)レベルでは:どのように個体がその生物的あるいは非生物的な環境によって影響されるか,そしてまた,それらに影響を与えるかを扱う。
個体群(population)レベルでは:特定の種の存在あるいは不在,その種が豊富か稀か,その個体数の変化の傾向や変動を扱う/2つのアプローチ=まず個体の属性を扱い,それからこれらがどのように結合して個体群の特徴を決定しているのかを考える vs 直接個体群の特徴を扱い,それからその諸側面を環境と結びつける(※頻度と分布を調べるという点で,疫学との類似性に注意)
群集 (community)レベルでは:群集の成分あるいは構造を扱い,それから群集がどのようなエネルギー,栄養素,他の化学物質の経路を通るのか(群集の機能)を扱う/2つのアプローチ=その群集を構成する個体群を考えることでパタンやプロセスの理解を追求 vs 直接群集自体の性質(種多様性,バイオマスの産生速度など)を観察
人間を含む生態系の中で健康影響を捉える場合,自然界の個体,個体群,群集だけでなく,人工の環境や,人間の影響を受けた環境や,人間の自然への影響(環境汚染や地球温暖化など)も扱わねばならない。
生態系内の物質循環(material cycle)とエネルギーフロー(energy flow)を把握することが重要だが,環境保健の中ではとくに生態毒性学(ecotoxicology)と呼ばれる分野の研究が盛んに行われてきた(例えば,水俣病発生地域内で,いろいろな生物体内の水銀濃度を調べて,どのような経路で水銀が生物から生物へ移行してヒトや猫に神経症状を起こさせたのかということや,五大湖周辺でDDTについていろいろな生物体内での濃度を調べたものなど)。
もちろん,毒物ばかりでなく,窒素循環や炭素循環など,どの生物にも存在するような元素の循環を調べる研究もある(かつてはCNコーダーという機械がよく使われていたが,現在では安定同位体組成の分析をするために質量分析計も使われる)。
産業革命以降,人間の環境形成作用が過大になり,自然生態系の物質循環を破壊したときに環境汚染や公害問題が起こってきた。
日本では1960年代からの高度経済成長期には重化学工業が盛んになったため,各地で公害病が起こった。1967年に公害対策基本法ができ,1972年に汚染物質排出規制がなされたため,目に見える公害問題は下火になってきた。が,それに代わるように地球規模の環境問題が20世紀末からクローズアップされだした。いくつかを次に挙げる。
「ヒトは周囲に自らの生存に適した環境を一時的に作り出したり,外部環境を大規模に改変したりすることで,本来の物理化学的環境条件が生存に適していない居住場所にまで,その生息域を広げてきた」と考えるとき,衣と住はまさに「ヒトが周囲に作り出した自らの生存に適した環境」といえる(言い換えると,衣服と住居によって環境をコントロール可能にした)。
食についても,ヒトは,農耕や牧畜によって食料となりうる生物の現存量を調節し,本来その環境にはなかった生物を持ち込み,育種や遺伝子組換えによって形質を改変したばかりでなく,加工によって保存を可能にした。加熱して軟らかくしたり,殺菌したり,発酵させたり,冷凍したり燻製にしたり,ありとあらゆる手段を使って食物をコントロールし,確保しているといえる。
現代の日本では,人間の健康で文化的な生活を確保するため,衣食住に関してもさまざまな法律や制度が定められている。一方,身近な問題であるだけに,世間一般の関心も高く,マスコミ等で騒がれる度に,それに対応して法制度が継ぎ接ぎされてきたという側面も否めない。省庁間の整合性が十分でない点もあり,今後の改善が必要であろう。
しかし,見方を変えれば,衣食住の開発の歴史は,ヒトと自然環境の間に介在するもの(言語,技術,社会組織)を肥大化させてきたといえる。現代日本人が自然の変化に鈍感だったり,逆に危機感を抱きすぎてパニックを起こしたりするのは,自然との距離が遠くなったことの表出でもある。
少なくとも食に関してみれば,都市はたんなる消費地に過ぎず,生産はしていない(キューバのように,循環型都市有機農業を営んでいる国もあるので,こういうあり方は必然ではないが,現代日本の都市は食糧生産しているとはいえない)ため,都市住民は,自分が食べているものの素性を良く知らない。狩猟採集時代ならありえなかったことだ。やはり素性を知らないと安心できないということで,トレーサビリティ等が重視されるようになってきた。
衣料は,衛生面からみれば,衣服下の気候をヒトにとって快適な状態に保ち,汗や皮脂を吸着して皮膚の清潔維持に役立ち,機械的外力や紫外線や昆虫の刺咬などの有害作用から体を守るという保護作用をもち,人体にとっては有害でないことが重要。
一方,外から見える個人の属性なので,社会的な状態を示す機能ももっている。現代社会だけではなく,中世ヨーロッパの王侯貴族はきらびやかな衣服を着ていたし,日本の平安時代の十二単衣とかの例もある。これから何をするのか,という行動のサインにもなる。ミクロネシアのヤップ島の女性は生活の場面によって身に付けるべき腰蓑が異なり,日常身に付ける腰蓑はバナナやセンネンボク,ココヤシなどの葉から作った彩色しないもの(しかもタロイモ田が長老用,夫用,妻子用と分かれているので,それぞれ異なる腰蓑をつけて作業しなければならない),祭りのときはハイビスカスの繊維で作った赤や黄色に染めた腰蓑(階級の低い村の女性には許されない),と使い分けねばならなかった(出典:印東道子「オアセニア暮らしの考古学」朝日選書)。
繊維の吸湿吸水性,放湿性,通気性,帯電性,織り方の組み合わせにより,衣服下の気候がどのような状態になるかは違ってくる。
有機物に対する吸着性,吸湿吸水性,放湿性,通気性が良い繊維は,皮膚から汗や皮脂を除去する効果をもつ。
汚染物が付着しにくく,かつ透過しにくい繊維は,外部からの汚染を防ぐ。
織り方のきめが粗い布や有機物が付着した布や帯電性の大きい布には,汚染物が付着しやすい。
衣料用繊維の大部分には防縮,防虫,防菌,防カビ,染色などの加工がなされている。
防縮加工の過程ではホルムアルデヒドが使われる。発ガン性がある物質なので,衣類については溶出試験を行うことが法律で定められている(下記参照)。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」(1973年制定,1974年施行):家庭用品法と呼ばれる。ホルムアルデヒドや有機水銀化合物などを規制。家庭用品に使用される化学物質について,変異原性試験,亜急性毒性試験,皮膚刺激性・皮膚感作性試験,細胞毒性試験が基本的な毒性項目として実施され,生殖・発生毒性試験や吸入毒性試験が追加実施されることもある。抗菌剤では有機水銀化合物,トリブチル錫化合物,トリフェニル錫化合物の製造・使用が規制されている。
抗菌防臭加工については,繊維評価技術協議会(JTETC)などの活動を通して,業界が自主的にガイドラインを設けている。
食品の公衆衛生学的把握として,食品の管理は,食品を安全に食べられるようにし,食中毒などを起こさないことが基本であり,複数の省庁の複数の法律に規定されている。例えば食品表示について,農林水産省の所管するJAS法と厚生労働省の所管する食品衛生法では,規定が異なる。機能性食品については健康増進法で別に規定されている。
総合衛生管理製造過程は,食品衛生法(昭和22年2月24日法律第233号;平成20年5月現在,最終改正は平成18年6月7日法律第53号)第13条に,「製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう」と定義されている。
実際には,HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)(危害分析・重要管理点システムと訳される)による衛生管理及びその前提となる施設設備の衛生管理等を行うことにより,最終的な食品の検査ではなく,総合的に衛生が管理された食品の製造又は加工の工程を意味している。
HACCPは元々,NASAの宇宙食管理から出発(宇宙に食物をもっていくには究極のセキュリティが要求されるため)。マニュアル化されていることが利点であるが,弱点でもある。
最終製品の検査に重点をおいた従来の衛生管理とは異なり,食品の安全性について危害を予測し,危害を管理することができる工程を重要管理点として特定し,重点的に管理することにより,製品の安全確保を図る。具体的には、営業者が自ら次の各項により最終製品全体の安全を保証する(平成8年10月22日厚生省生活衛生局食品保健課長乳肉衛生課長通知)。
HACCP承認施設において不適切な運用によって食中毒事件が発生した事例もあるが,承認取得に向けた食品メーカの取り組みは増加しつつあった……わけだが,最近の食品偽装事件を見ると十分とは言いにくい(意図的に偽装されることを防げない。けれども一方では賞味期限の意味を問い直す必要があるかもしれない。もちろん消費期限とは区別して考える必要がある)。輸入食品についても規制が緩かったのは,最近の毒入り餃子事件が示す通り。
参考:日本缶詰協会による関係法規集,International HACCP alliance,WHOサイト内HACCP情報,食の安全推進アクションプラン(平成12年12月策定,平成14年2月改定)。
平成14年4月5日の閣議口頭了解に基づいて議論が重ねられ,平成15年2月に食品安全基本法が国会提出され,平成15年5月23日に成立したことを受け,平成15年7月1日に内閣府内に「食品安全委員会」ができた。
従来,農林水産省と厚生労働省がリスク評価とリスク管理の両方を担当してきたが,BSE問題がきっかけで,各省庁の影響を受けず科学的知見に基づき公正にリスク評価を実行できる組織の必要性が強く認識された。また,風評被害を避ける必要性が認識されたこともあって,国民からの不安や疑問を受け付け,リスクを正確にわかりやすく国民に伝える,リスクコミュニケーションを推進する組織も必要とされた。食品安全委員会は,その実現のために設置されたので,リスク評価とリスクコミュニケーションを所管し,リスク管理にはかかわらない。
つまり,HACCPによって安全な食品を製造しても,消費者が店頭で目にするまでに,どういう経路を通ってきた,どのように生産されたものかがわからないのでは片手落ち。店頭で目にする商品からそれを逆に追跡できること,つまりトレーサビリティが必要とされる時代になってきている。
(例)青果ネットカタログというシステムがある(食品総合研究所からのニュースリリース)。2002年8月23日に一般公開され,2003年1月から,イオングループ,コープこうべ,大地を守る会の協力で,消費者参加による大規模な実用化実験。消費者にとっては便利。今後,要求は高まると思われる。RFIDチップ付き包装のような技術によりコストも低下するであろう。
ただし狩猟採集生活をしていた頃から自給自足農業をしていた頃まで,人間の社会でも生産と消費は切り離されていないのが普通だったので,トレーサビリティという問題はありえなかった。都市生活をする「消費者」の出現によって,生産と消費が切り離されたのが問題の根源といえる。SEICAのような試みは,大規模流通によって切り離された生産と消費を,情報技術によってつなげるものである。しかし,それは何らかの基準で取捨選択された情報だけがつながれているのだということを忘れてはならない。
遺伝子組換え技術を応用して得られた食品。人為交配による育種でも自然に遺伝子の組換えが起きることもあるが,遺伝子組換え技術がそれと異なるのは,(1)種の壁を越えて他の生物に遺伝子を導入することができること,(2)品種改良の範囲を大幅に拡大できること,(3)期間が圧倒的に短いこと,である。これを程度の差と見るか本質的な違いと見るかは,意見が分かれている。
食品そのもの(但し綿も含む)と添加物がある。日本で厚生労働省が安全性審査をしたものは,2003年7月1日時点で55食品12添加物,2008年2月12日時点で88食品14添加物(安全性審査の手続を経た遺伝子組換え食品及び添加物一覧)。
遺伝子組換え技術については,生産者,消費者,技術開発者等,立場によってポイントが違うことを意識すべき。
厚生労働省医薬局食品保健部,遺伝子組換え食品ホームページ:安全性審査の手続き(挿入遺伝子の安全性,挿入遺伝子により産生されるタンパク質の有害性の有無,アレルギー誘発性の有無,挿入遺伝子が間接的に作用して他の有害物質を産生する可能性の有無,遺伝子を挿入したことにより成分に重大な変化を起こす可能性の有無,等について,申請者が提出した資料が専門家によって審査される。2001年4月1日以降,安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品又はこれを原材料に用いた食品は,輸入,販売等が法的に禁止されている),表示についてなど,さまざまな情報がまとめられている。
米国は規制に消極的。ヨーロッパ諸国は警戒姿勢(EU議会では遺伝子組換え作物(Genetically Modified Organismを略してGMOと書く)や遺伝子組換え食品についてトレーサビリティの必要性が提案され,2002年秋に採択されている)。
食品の特別の用途や効能についての表示は,健康増進法(以前は栄養改善法)第26条から第32条で規定。
健康増進法で指定されている食品を総称して特別用途食品と呼ぶ。「乳児用,幼児用,妊産婦用,病者用等の特別の用途に適するもの」に加え,「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し,その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする」特定保健用食品も特別用途食品。いわゆる機能性食品は,効能があるという表示をするなら,特定保健用食品として表示されることになる(個別に厚生労働大臣の許可を受けないと表示できない点に注意)。
市販ベビーフードについては,平成8年に各都道府県知事,政令市市長,特別区区長あてに,厚生省から通知されたベビーフード指針がある。ベビーフードの中でも,アレルゲンを除去することにより,アレルゲン除去食品として特別用途食品の認定を受けているものがある。
コーデックス委員会(FAO/WHO合同の国際食品規格委員会)が食品の健康強調表示について活発に議論している状況から, 2001年2月26日に薬事・食品衛生審議会から答申を受け,厚生労働省は,2001年4月から,いわゆる健康食品のうち一定の条件を満たすものを「保健機能食品」と称することにした(保健機能食品制度の創設について(平成13年),「健康食品」に係る制度の見直しについて(平成17年))。規格基準を満たせば許可や届け出なく成分表示できる栄養機能食品「高齢化や食生活の乱れなどにより,通常の食生活を行うことが難しく,1日に必要な栄養成分を摂れない場合など,栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨とした食品」もある。
栄養表示基準は,健康増進法第31条の1に基づいて,細かく定められている。「栄養機能食品」の表示については,食品衛生法施行規則第5条第1項第1号ユの規定に基づいて,2001年 3月27日付け厚生労働省告示(第97号)で定められている。
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
他にもいろいろある。
いわゆる環境ホルモン。DDTの慢性毒性は古くから指摘。DESシンドロームも1970年。クローズアップされたのは1996年の「奪われし未来」。その後,厚生省の1996年度厚生科学研究事業「化学物質のクライシスマネジメントに関する研究班」,環境庁の1997年「外因性内分泌攪乱化学物質問題に関する研究班」,1998年「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」を経て,1999年にはダイオキシン類対策特別措置法が成立した。
環境ホルモン学会(正式名:日本内分泌撹乱化学物質学会)が1998年6月に発足。
しかし,SPEED'98でリストに載った物質のうち,懸念された内分泌攪乱作用をはっきりと示したものはほとんどなかった。最近は騒ぎすぎだったのではないかという風潮が強い。
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」として,OECD勧告を受けて1999年に制定された。PRTR制度とMSDS制度からなる。
PRTR (Pollutant Release and Transfer Register)は「有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組み」
MSDS(Material Safety Data Sheet)は事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため,対象化学物質を含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には,その化学物質の性状及び取扱いに関する情報を,化学物質安全データシート(MSDS)として事前に提供することを義務づける制度
世論の盛り上がりを受けて1999年に制定された。環境省が1999年に発表した基本的考え方では,ダイオキシン問題は将来に渡って国民の健康を守り環境を守るために内閣をあげて取り組みを一層強化しなければならないものであり,4年以内に排出総量を9割削減,所沢で見られたような風評被害への対策,TDIを始めとするする各種基準作りなどが緊急に必要であるとされている。
問題になった当初のダイオキシン測定値(多くは摂南大学の宮田教授らによるもの)がおかしいという指摘や,ごみ焼却よりも農薬起源の汚染がメインだったというレポート(宍道湖の底質中ダイオキシン類の異性体組成などの分析結果による)が横浜国立大グループ(益永,中西ら)から出て,この法律の有効性を疑問視する声も高まっている(参考:渡辺・林「ダイオキシン:神話の終焉」日本評論社, 2003年)。
2000年末のダイオキシン特別措置法施行によって一般廃棄物や産廃焼却炉の厳しい排ガス規制が始まったが,2003年になってもダイオキシン類曝露による健康リスクはほとんど変わらない(コストはかかっている。心理的には違うかも?)。変わらない理由としては,(1)リスクの大きさが体内に蓄積されているダイオキシンに依存,(2)ダイオキシンの生物学的半減期が長い,(3)ヒトの体内への主たる経路は食品(魚介類からが7割),(4)魚介類中のダイオキシンも環境に残留しているものの影響が大,(5)ヒトに摂取されるダイオキシンの6〜7割はPCDD/Fsでなくco-PCB,(6)焼却炉排ガスのダイオキシン類のうちco-PCBは5%程度(co-PCB源は捨てられたPCB製品かもしれない),(7)環境中の残留PCDD/Fsは過去に使われた農薬由来が主,といったことが挙げられる。そう考えると,排ガス規制は的外れだったといわざるをえない。
代替リスク回避策としてはコストベネフィット分析の結果,ディーゼルの排ガス対策が有効とわかっている。他の対策として言われていることのうち,母乳をやめると免疫機能低下などで余命損失は増えるのでダメ。ダイオキシン濃度が高い魚介類を控えるのも代わりに肉をとったらコレステロールが高くなるとか,ダイオキシン濃度が低い魚介類をとったらメチル水銀が増えそうだとか,肉も魚介類もとらないと低タンパクになるなどの理由でダメ。
森林減少,オゾンホール,地球温暖化など,すでに説明した問題のほかにも,資源の枯渇,人口爆発,生物多様性の減少等,多くの地球規模の問題が起こり,国際的な取り組みが必要とされる。
公害問題については,昭和47年(1972年)スウェーデンの首都ストックホルムで,国連主催の環境問題国際会議が開かれた。それと並行して民間の国際環境会議も開かれ,宇井らにより日本の公害問題の総まとめが行われた。公害病患者自身が世界に向けてアピールし,公害の悲惨さが世界中で認識されるようになった(が,日本のマスメディアの扱いは小さかった)。
今日の地球環境問題への取り組みは,国連(例えば国連環境開発計画(UNEP))を中心として,各種の政府間パネルや,NGOによって活発に行われている。フロンガス排出を規制するモントリオール議定書(1987年),IPCC(気候変動に関する政府間パネル),COP(気候変動枠組み条約締約国会議),POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)などが有名。
環境には認識しやすい環境(対応する感覚受容器がある外部環境)と認識しにくい環境(体内の環境や,感覚受容器がない外部環境)がある。認識しにくい環境でも機械を使って調べれば認識は可能。
外部環境が変化したとき,感覚受容器がそれを検知すると,ネガティブ・フィードバックが起こって,内部環境は元の状態に保たれる。それによって内部環境が比較的一定の状態に保たれることを,恒常性の維持(homeostasis)という。
外部環境→内部環境→外部環境という物質の流れを分解してみると,曝露,吸収,分布,代謝(主に肝臓),排泄という過程を辿る。それぞれの移行確率は100%ではない。偶然のばらつきもあるし,物質によっても違うし,臓器によっても違うし,個人差もある。個人差は,遺伝素因もあれば,生活史上の環境要因から受けた影響の蓄積もあれば,認識される外部環境に対してとる行動の違いもある。
外部環境からの曝露刺激の量=dose(用量,曝露量)
生体が吸収した後,運ばれる臓器はさまざま。ある曝露刺激物質が主として作用する臓器を,その物質の標的臓器とか決定臓器と呼び(例えばカドミウムなら腎臓とか),doseに対して(または血中レベルに対して)標的臓器がどのような影響を受けるかという関係を量-影響関係と呼ぶ。
影響には,回復不可能な影響と,一時的機能障害を起こすが回復可能な影響と,機能障害を起こすほどでもなく代謝によって調節可能な影響の3段階がある。
生体にいかなる影響も及ぼさない曝露量を無作用量とか無影響量といい,NOEL(no observed effect level)と略記する。それに対して有害作用が検出されないレベルを無毒性量,即ちNOAEL (no observed adverse effect level)という。NOELやNOAELが定義されるのは用量反応関係に閾値がある場合に限られる。なお,毒性のある最小の影響量は通常,最低毒性量(LOAEL)と呼ばれる。
個人レベルでみた場合,無毒性量以下の曝露ならば毒性は発現せず,最低毒性量を超えると,曝露量が多くなるほど強く毒性が発現すると考えられる。このような関係を閾値のある用量反応関係という。無毒性量を不確実性係数で割って一日耐用容量(Tolerable Daily Intake; TDI)を求め,一日摂取量をTDIで割った値であるハザード比(Hazard Quotient; HQ)が1より大きければ「リスクあり」,1以下なら「リスクなし」と判断するのが古典的な考え方。
集団レベルでみると,有害物の負荷量としてのdoseに対する反応割合との関係は,S字状カーブになることが多い。反応(感受性)に個体差があることがS字状になる原因。S字曲線は,通常,累積対数正規分布で近似される。半数の個体が反応を示す負荷量を半数影響量ED50と呼ぶ。急性毒性試験ではLD50が良く使われ,推定にはプロビット分析やロジット分析が使われる場合が多い。環境リスク評価では用量-反応関係を示す対数正規分布の左裾確率と曝露量の確率密度関数の積和によって,リスクを算出することもある。
低用量域でのリスクを,何らかのモデルを使って定量的に推計できるようなアセスメントを確立し(外挿になるので正しい保証はないが他に方法がない),マネージメントとしてはリスクをある一定のレベル以下に抑えるような基準値を定める必要がある。
発ガンのモデルには以下のようなものがある。
環境保全は,人類の存在そのものや生活の利便性,福祉といったものと相反する面があるので,環境保全策を実施するには,環境保全の効果と他の面への(多くの場合負の)効果(しかも人や地域によって異なる)をうまく調整しなければならない。この調整が環境リスク管理(環境リスクマネジメント)の役割
環境リスク管理(環境リスクマネジメント)は,(1)環境リスク削減を目的,(2)その削減策がより大きな別のリスクを生まない,(3)限られた資源の下で削減の優先順位をつける,(4)他の原因による健康リスクや生態リスク削減策との整合性を考える,が必要。
健康は社会の文脈に依存しているので,健康リスクの評価は相対的にしかできない。公衆衛生や栄養の水準が低ければ,少しコストをかけてそれらを向上するという健康リスク対策をするだけで,それらの改善と同期して平均寿命や健康寿命は延びる(集団レベルで健康になるといえる)。が,既に公衆衛生や栄養の水準が高くなって,低栄養や感染症による死亡がほとんど見られなくなったあとは,健康リスク対策に金をかけても効果がさほどあがらない。
南北間で資源を移転すると世界レベルの健康リスク削減は効果的に行われることになる(ODAのrational)。先進国は健康リスク削減と同時に生態リスク増加が起こった。
「リスク」については,扱われる分野によって概念が違うことに注意。疫学では,ある集団を一定期間観察したとき,その期間中に何らかのイベントを経験する人の割合をリスク(あるいは累積発生率)と呼ぶ。が,リスク論では,「リスクとは望ましくない事象とその生起確率を示す概念」という把握で大方問題ないと思われる。
外部環境のそれぞれの因子について,量-影響関係や量-反応関係に関する知見をまとめて整理したものを,環境の質の判定条件と呼ぶ。この条件と曝露量のアセスメントを元にして,各因子のリスクを判定する。ここまでがリスクアセスメントである。
判定されたリスクと,環境リスク以外の要因の分析結果(社会,経済,技術などの制約条件。ここにLCAやCVMも含まれる)を統合して行政判断が行われ,ガイドラインや勧告が出され,その中で基準値が決められる。この段階がリスクマネージメントに該当する。
アセスメントとマネージメントの主体は別であるべき。
人は誰でもいつかは死ぬので,死をエンドポイントとすると,低いリスクの削減効果をみるためには長い観察期間が必要となって,観察からの脱落が増えてまずい。死亡そのものでなく,死によって失われた寿命の長さを評価するのが損失余命という考え方
米国環境保護庁が環境問題の優先順位付けのために開発した手法。ある地域に関する環境問題の包括的なリストを作成し,問題の影響の大きさをリスクの側面から比較評価して(この際,健康リスクだけでなく,生態系リスクや生活の質へのリスクなども加味)ランクをつける。
評価するのに専門家だけでなく,市民代表など幅広い人が参加して住民の立場からの意見も取り入れる点が特徴。
(例)国立環境研究所が中心になって,環境庁,地方自治体,大学,コンサルタント,環境研究所から,関係者24名がパネルとなって,年2回泊り込みで,環境問題のリストづくりとランクづけをした。結果は15の問題領域[地球規模の大気変動,有害化学物質汚染,電磁波・放射線など]ごとの4つの側面[健康,生産,生物,精神]への影響の大きさの,参加者の平均値として得られた(高月紘「自分の暮らしがわかるエコロジー・テスト」講談社ブルーバックス参照)
日本語では仮想評価法と呼ばれる。環境(健康を含む)の価値を仮想的な金銭に換算して考える。即ち,リスク削減のためにいくらなら払ってもいいか(支払い意思額:WTP),いくら貰えばリスクが増えてもいいか(受入れ補償額:WTA)をアンケートで調べる
健康リスクならQOLをみるような場合に使われる。環境リスク評価には良く使われる。欧米では裁判でも使われる(例:バルディーズCVM評価)
限界:仮想の妥当性,とくに日常的に現金経済に接していない人が対象の場合のWTPとWTAの不一致,質問のバイアス等
予防原則:毒性があることが証明されていなくても危険がありそうな十分な根拠があれば対策する必要はあるとする考え方。2000年2月にEU委員会から報告された文書によれば,疑わしきは何でも禁止ということではなく(ゼロリスク論だとそういうことになるが,そんなことをしたら現代社会は存続できない),予防原則を適用するためには,均衡性,非差別性,整合性,費用便益分析,再検討,挙証責任が満足されねばならないとされる。
大雑把にいえば,科学的に正当に評価して,対策することによって期待される便益が対策にかかる費用に見合うような場合に,差別なく適用されるべきだということ。グリーンピースなどからは批判されているが,リスク研究者は概ねEU委員会の方針を妥当としている。
リスクコミュニケーション:「あるリスクについて直接間接に関係する人々が意見を交換すること」…上意下達でなく議論を通して相互理解を図るのがポイント。
リスクマネージメントにおいて環境リスク以外の要因の分析結果を取り込む際に,Public Involvementは当然行われるわけだが,その際,リスクコミュニケーションがうまく取れるかということが非常に重要
環境認識を意識すると意思疎通という話に戻ってこざるを得ない。環境倫理学でいうところのenvironmental justiceとも絡む。人間の価値観の多様性が根底にあるので,互いに異なる価値観の存在を認め合わないとコミュニケーションは成立しない。その上で利害の調整や合意形成がなされる。ゼロリスク論はコミュニケーションの余地が無い。
意思疎通の方法として,いろいろなガイドラインが提案されている。例えば,主催者,司会者,参加者それぞれの立場を考慮した,環境省「リスクコミュニケーションチェックシート集」